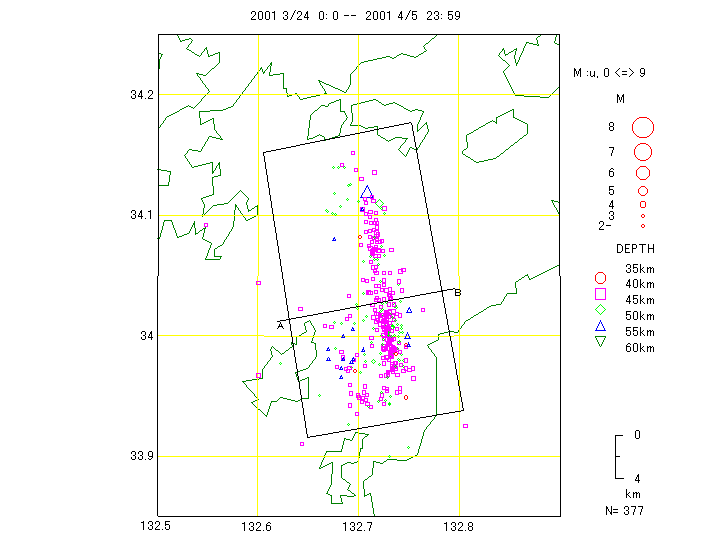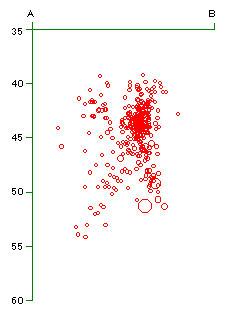芸予地震の震源分布を比較
図1:再計算された結果:新走時表+新ウエイト(上野寛さんによる)
全体を南北の二つの領域に分けて断面を示したものと、全体の断面(左端)とがあります。この図であれば西傾斜をすんなり理解されると思います。
図2:左図が従来の走時表(83A)で従来の決定法(地震年報震源=公開されているもの)
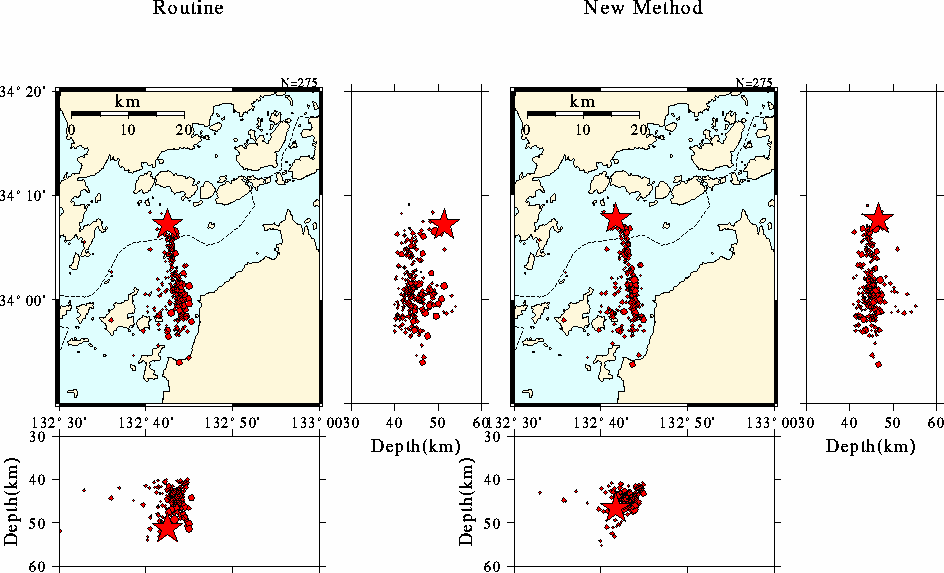 京大防災研での研究集会で地震予知情報課橋本徹夫調査官が発表で用いて参加者に誤解をまねいた図が、この左側とほぼ同じと思います。この図では、本震が大きな☆で示されているので分かりずらいですが、これが無ければ石橋さんの指摘されたように東傾斜にも見えます。
京大防災研での研究集会で地震予知情報課橋本徹夫調査官が発表で用いて参加者に誤解をまねいた図が、この左側とほぼ同じと思います。この図では、本震が大きな☆で示されているので分かりずらいですが、これが無ければ石橋さんの指摘されたように東傾斜にも見えます。
右側の図は、新方式によります。図1は、これに観測点補正値を導入したより良い結果。
図3:従来の走時表(83A)で従来の決定法
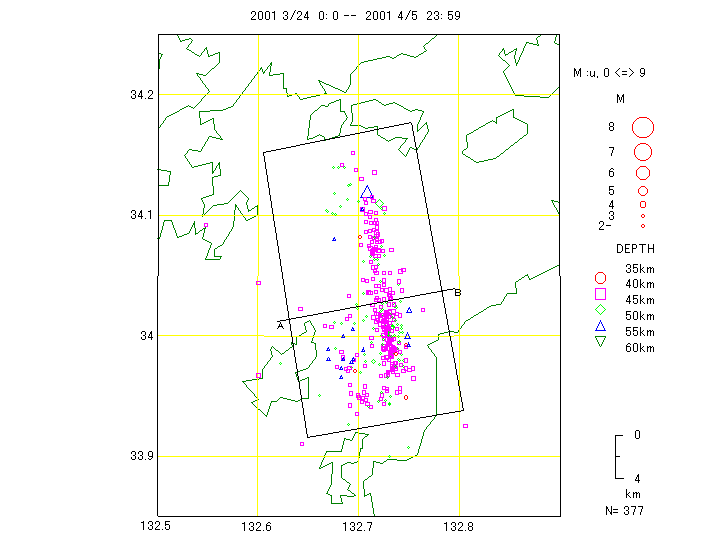
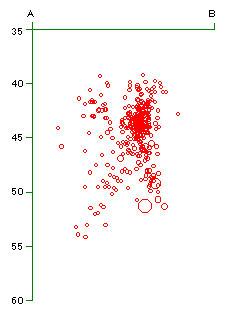
図2のデータと同じですが、断面を切る方向を余震分布の長軸に直交する方向に取った。大きなイベントは観測されるデータが遠くまであるため、これまでの震源決定計算では、遠くのデータが震源の深さをより深くしているので、大粒のイベントが他より深く決まり、断面図を見る際に誤解を招きやすくなっていた。それでこれまでは観測点補正値などを導入してより正確な分布を調査資料に用いていた。芸予地震でも図1に近い分布が得られている。
戻る
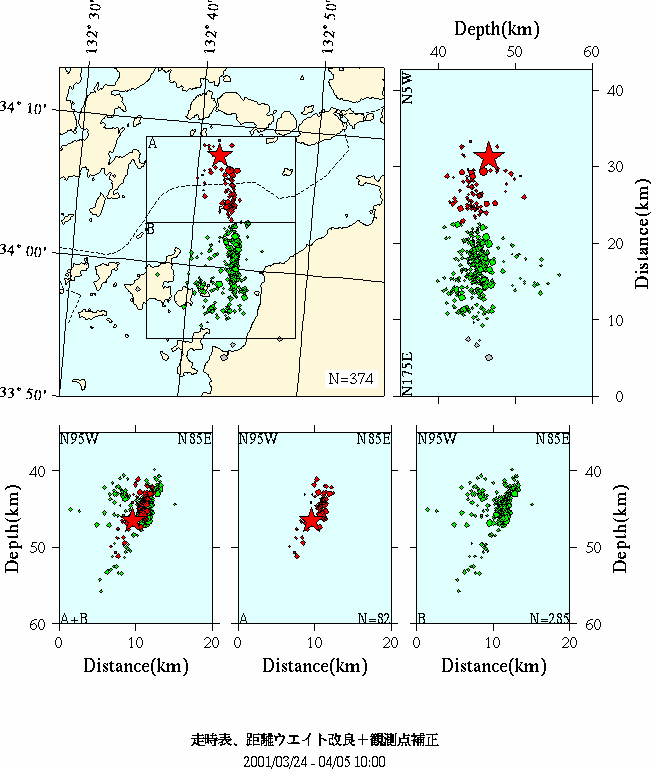
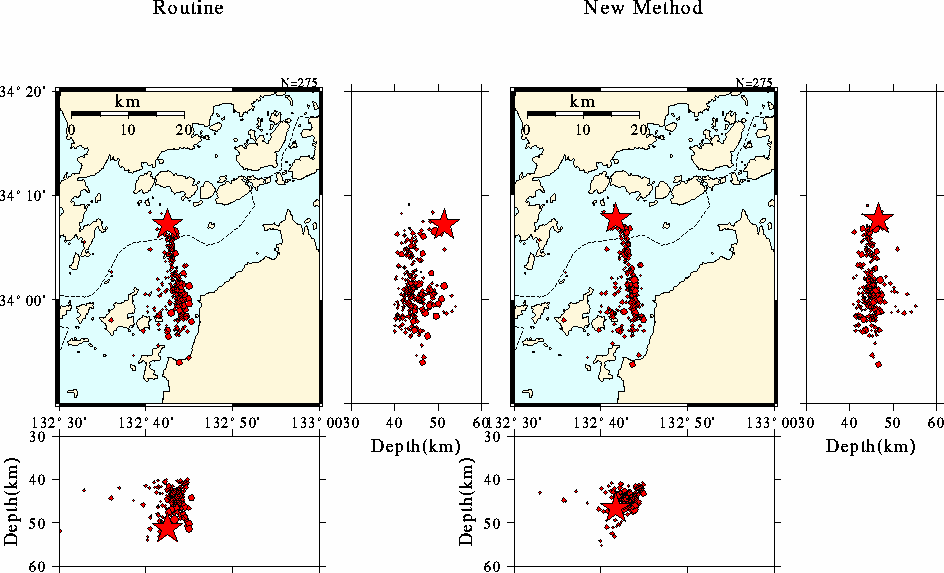 京大防災研での研究集会で地震予知情報課橋本徹夫調査官が発表で用いて参加者に誤解をまねいた図が、この左側とほぼ同じと思います。この図では、本震が大きな☆で示されているので分かりずらいですが、これが無ければ石橋さんの指摘されたように東傾斜にも見えます。
京大防災研での研究集会で地震予知情報課橋本徹夫調査官が発表で用いて参加者に誤解をまねいた図が、この左側とほぼ同じと思います。この図では、本震が大きな☆で示されているので分かりずらいですが、これが無ければ石橋さんの指摘されたように東傾斜にも見えます。